公認会計士になるためには、専門学校の学費以外にも様々な費用が掛かります。
では公認会計士を目指す受験生は、どれくらいのお金を準備しておけば良いのでしょうか。
これから公認会計士を目指す方は必要な学費やその他の費用を把握して、必要なお金を予め準備するようにしてください。

専門学校の学費
公認会計士になるために必要な費用のうち、最も大きいものが専門学校の学費です。
専門学校の学費は各専門学校や選択するコースにより異なります。
参考までに各専門学校の初学者向けの一般的な公認会計士講座の学費は以下のとおりです。
【各専門学校の学費】
| 区分 | TAC | 大原 | クレアール | LEC | CPA |
| 1.5年L本科生 | 入門1.5年オータム本コース | 2年スタンダード合格コース | 短答+論文合格コース | 1.8年スタンダードコース | |
| ライブ/個別DVD | 740,000円~ | 740,000円~ | ー | 274,640円~ | 790,000円~ |
| Web通信 | 740,000円~ | 740,000円~ | 366,000円~ | 257,360円~ | 648,000円~ |
| DVD通信 | 820,000円~ | 830,000円~ | 411,000円~ | 343,760円~ | ー |
※ライブは教室で生講義を受講する受講形態、個別DVDは個別ブースでDVDを視聴する受講形態です。
※LECは短答合格コースと論文合格コースはそれぞれ別のコースになっているのですが、短答合格の場合は、論文合格コースを奨学生価格50,000円で受講可能となっているため、比較のために短答合格コースの受講料に50,000円を加算して記載しています。
多くの受験生が通っているTACや大原の初学者通学コースを申し込むと、70万円から80万円程度の学費が掛かります。
この学費が準備できず、独学で公認会計士を目指す人もいるのですが、独学で合格できるほど、公認会計士試験は甘くありません。
もし学生の方で親御さんにサポートをお願いできるのであれば、頭を下げてお願いして学費を支援してもらいましょう。
あるいはもし自分で資金を準備しなければならないなら、学習を始める前に月10万円のアルバイトを7か月行って、学費を準備するようにしましょう。
このようなことは、一見遠回りのようにも見えますが、専門学校をうまく利用して、最短で公認会計士になるようにしてください。
通学のための定期代
専門学校の学費以外に必要な費用として、通学のための定期代があります。
専門学校には、講義のない日でも自習のために、ほぼ毎日通うことになります。
従って専門学校までの交通費もバカになりません。
大原は通学定期が使えるコースもありますが、TACでは通勤定期を購入することになります。
往復600円程度の距離で通勤定期だと、最も安くなる6か月定期で50,000円程度になり、年間で100,000円程度必要になります。
決して安くない金額になりますので、学費以外にも通学のための交通費も考えておくようにしてください。
書籍代、文房具代
学習は専門学校のテキストを使って行いますので、基本的に書籍代はかかりません。
ただし試験用の条文集や監査六法などについては、自分で用意する必要がありますので、これらの書籍代は必要になります。
また論文式本試験では解答はボールペンで記入することになるので、普段の答練等でも慣れておくためにボールペンを使って答案を作成します。
そのため答練等では修正テープも必需品になるのですが、こういった文房具代も必要になってきます。
さらに専門学校の講義をWebでフォローする場合などは、PCやタブレット、スマホ等が必要になります。
新しいものは必要ありませんが学習を始める前に持っていなければ、購入することが必要です。
必要な方は学費以外にもこれらの費用を予め考えておくようにしてください。
昼食代、夕食代
学習を始めると朝から晩まで専門学校で講義を受けたり、自習することになります。
そのため昼食や夕食の食事代も学費以外に必要となってきます。
コンビニを利用したりして、なんとか一食500円程度に抑えたとしても、一日で1,000円、年間で350,000円程度が必要となります。
これらの費用は弁当を持参することによって抑えることも可能ですので、実家から通われる方は親御さんに弁当を作ってもらうのも一つの方法です。
受験手数料
それほど高額なものではありませんが学費以外に必要な費用には、試験を受験するための受験手数料があり、19,500円となっています。
第Ⅰ回短答式試験に合格できず第Ⅱ回短答式試験を受験する場合は、再度受験手数料を支払う必要がありますので、留意してください。
その他費用
その他学費以外に必要な費用には以下のようなものがあります。
- 情報交換のための飲み会の参加費用
- 気分転換のためのお小遣い
受験生が飲み会に参加するなんてと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、受験仲間との飲み会は、貴重な情報交換の場でもあります。
頻繁に参加する必要はありませんが、たまには同じ目標に向かって頑張っている受験仲間との飲み会に参加して、学習方法などの情報交換を積極的に行うことを、おすすめします。
また途中何度か気分転換して、モチベーションを維持していくことになります。
気分転換など必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、1年間という長丁場を乗り切るためには、うまく気分転換することも集中力維持のためには必要です。
従ってこれらの費用についても、ある程度予定しておいた方がよいでしょう。
100万円程度のお金が必要
昼食は弁当を持参するなどして、できるだけ出費を抑えるようにするならば、授業料を合わせても100万円程度の資金があれば、なんとかなります。
受験期間中は学習に集中すべきなので、アルバイト等をしている時間はありません。
繰り返しになりますが、親御さんにサポートをお願いできるなら、お願いするようにしてください。
あるいは自分で資金を準備しなければならないならば、学習開始後は学習に集中できるように必要な資金は予め準備しておくようにしてください。
これらの費用は合格後に簡単に回収できる
合格前の100万円は大きな金額ですが、試験に合格し監査法人に就職すれば、初年度から年収500万円はもらえます。
また監査法人に入所後、7~8年経ってマネージャーになる頃には、年収は1,000万円を超えるようになっています。
これらの公認会計士になるための費用は、合格後に簡単に取り返すことが可能です。
大事なのは一年でも早く公認会計士試験に合格することです。
必要な資金は親御さんに支援してもらうなり、予め準備するなりして、短期決戦で試験に挑んで合格を勝ち取るようにしてください。
公認会計士に最短ルートでなりたい人は、以下の記事も読んでみてください。

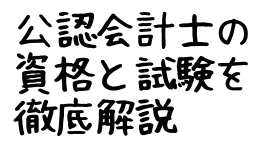
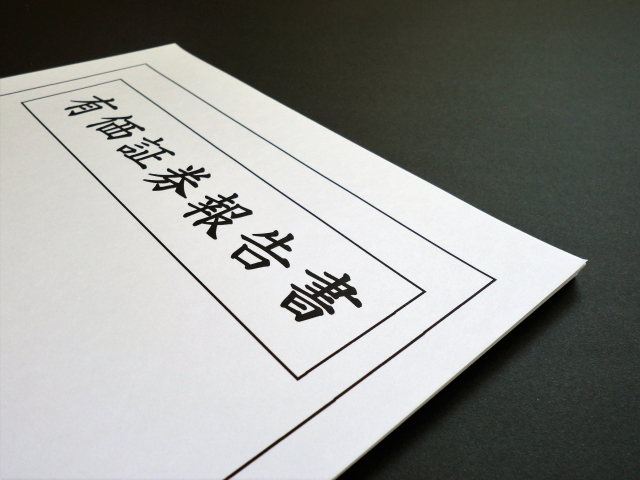
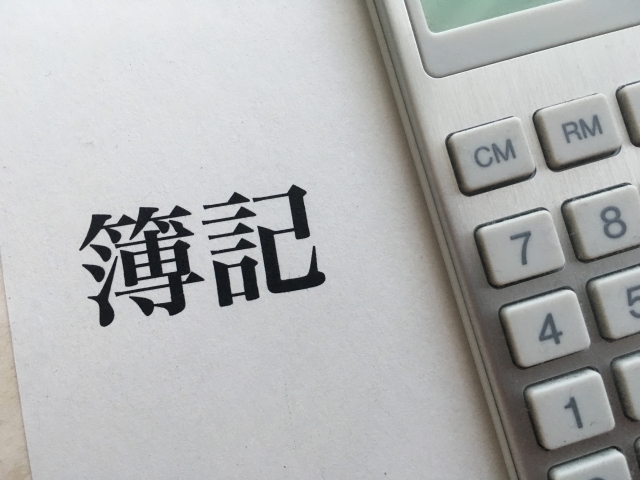
コメント