オックスフォード大学と野村総研が共同で、601種類の職業ごとにAIなどのコンピューター技術による代替可能性を試算し、2015年12月にその結果を公表しました。
そこでは、日本の労働人口の49%が就いている職種において、技術的には人工知能やロボットなどに代替される可能性が高いとしています。
そのリストの中に「会計監査係員」があったことから、将来、公認会計士の仕事が人工知能に代替されるという間違った認識が一時、広がってしまいました。
確かに今後、さらに人工知能(AI)の研究が進めば、公認会計士はその業務において人工知能(AI)を積極的に活用していくことになります。
でも公認会計士が不要とされるようなことは、企業経営自体が人工知能(AI)に代替されるような世の中にならない限り、ないと断言できます。
将来公認会計士の仕事が人工知能(AI)に奪われてしまうと主張している人たちは、残念ながら公認会計士の業務をよく分かっていない人たちのように思います。
人工知能(AI)に代替される領域
大手監査法人などは、監査の効率性や有効性を高めるために、人工知能(AI)の活用研究に積極的に乗り出しています。
この研究がもっと進めば、現在公認会計士が手作業で行っている監査手続の多くを自動化されることになるでしょう。
特に会計処理が画一的になされるような監査領域については、自動化される可能性が高いといえます。
例えば売上高の検証は取引は大量に反復して行われていますが、会計処理は画一的になされる領域であることから、監査手続の自動化は真っ先に試される領域と思います。
また会計上の見積項目の検証は比較的自動化が難しいと思われる項目ですが、その中でも貸倒引当金の妥当性を確かめる監査手続などは、自動化される可能性が高いといえます。
なぜならば貸倒引当金は貸倒実績率等の過去情報に基づき回収不能額を見積もっているものであり、企業が採用した見積方法を検証し、再計算することはそれほど難しいことではないためです。
変質する公認会計士の業務
このように人工知能(AI)による作業の代替は、早晩起こると思われます。
公認会計士はこの現実を受け止め積極的に人工知能(AI)を活用して、自らの業務の有効性、効率性を高めていくことが必要です。
人工知能(AI)が活用されている社会において公認会計士に求めるものは、今とは異なっているはずです。
しかしながら企業経営は人間が行うものである限り、経営者の経営判断や投資判断に対する評価や、経営者の誠実性に対する評価などは、どれだけ人工知能(AI)が進化したとしても、人間である公認会計士の監査人としての総合的な判断が必要とされる領域です。
その時代に求められる役割を果たすことによって、公認会計士は今後も社会のインフラとして必要とされる存在であり続けるのだと思います。
日本公認会計士協会の解説動画
公認会計士の仕事がAIに取って替わるというような誤ったうわさが無責任に流れたことから、日本公認会計士協会においてもAIが業界に及ぼす影響についての解説動画を作成し、公表しています。
AIが公認会計士業界に及ぼす影響について正しく理解したい方は、こちらの動画も見ていってください。
合格者数が高止まりしている今は、公認会計士になる絶好のチャンスです。
公認会計士になりたい人は、以下の記事も読んでみてください。

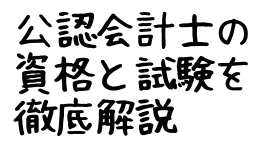
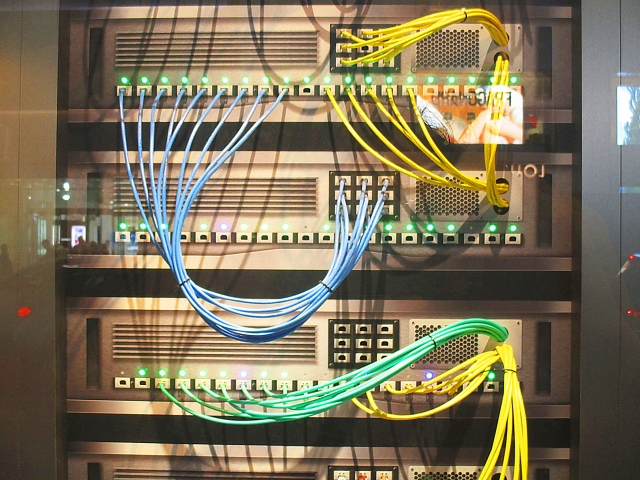
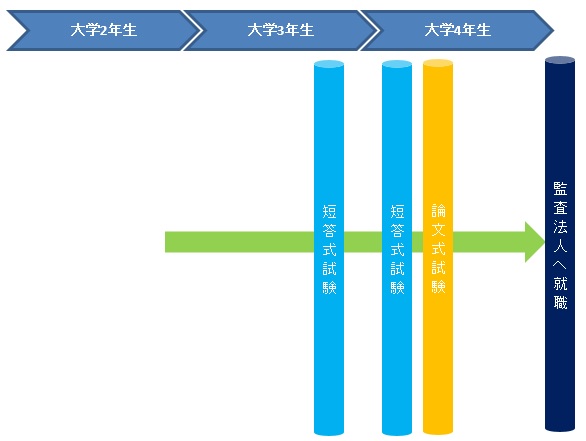
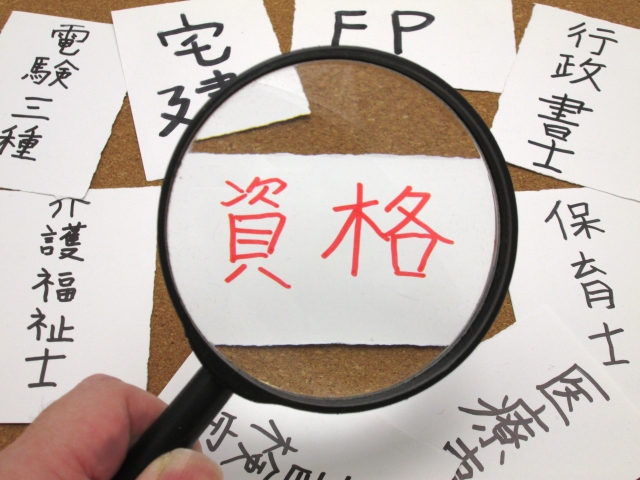
コメント